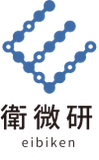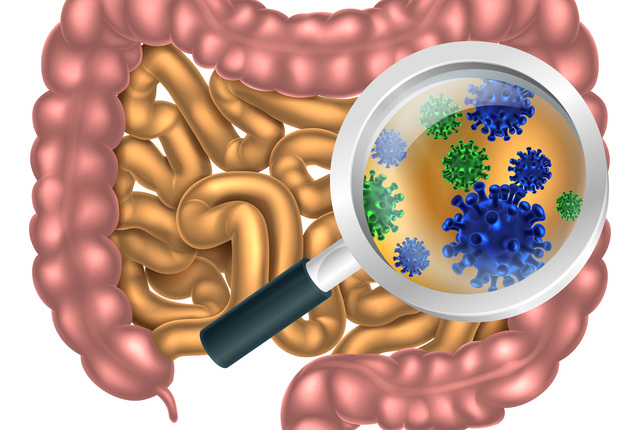わたしたちの体にはたくさんの「常在菌」が存在する
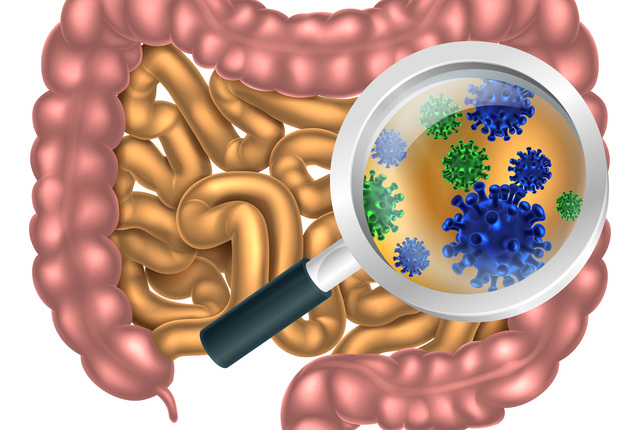
わたしたちの体には、目に見えない微生物がたくさん存在しています。その数は、わたしたち自身の細胞の数(約37兆個)をはるかに超える、数十兆~数百兆個といわれています。
特に、皮膚や口腔内、腸といった「体の外」とつながる場所にいる微生物は、わたしたちと共生関係にあり、ふつうは害を及ぼすことはありません。このような微生物は「常在菌」とよばれます。もはや、わたしたちの健康には欠かせない、大切なパートナーといえます。
常在菌はどこにいるの?
口腔内
口の中には、数百億個もの微生物が存在します。虫歯の原因となる「ミュータンス菌」や歯周病の原因となる「ジンジバリス菌」などが有名です。歯の表面にある歯垢には、1 gあたり数百億個、唾液1 mL中には、数百万〜数十億個もの細菌が存在しています。
皮膚
皮膚には、数兆個もの微生物が存在します。表皮ブドウ球菌や黄色ブドウ球菌のほか、アクネ菌、水虫の原因菌の一種とされる白癬菌などが知られています。これらの常在菌は、外部からの刺激や病原菌の侵入を防ぐバリアの役割を果たすなど、わたしたちの皮膚の健康を守る大切な働きをしています。
消化管内(腸・胃など)
大腸は、微生物にとってはまさに「大都会」といえます。大腸菌、ビフィズス菌、乳酸菌など数百種類、数百兆個もの多様な微生物が存在しています。大腸の粘膜表面を広げると、テニスコート一面分にもなります。そのような広大な場所で、たくさんの微生物が活動しているわけです。わたしたちの糞便の約半分は腸内細菌といわれるほど、大腸は微生物で満ち溢れています。
その人だけの「微生物の生態系」、つまり「腸内フローラ(お花畑)」ができあがります。この腸内フローラの基本的な構成は、だいたい3〜5歳頃までに決まるといわれています。
逆に、胃の中は胃酸によりとても強い酸性に保たれているため、多くの細菌は生きていけません。存在する菌の数は胃液1 mLあたりわずか数百~数千個程度です。「ピロリ菌」や「乳酸桿菌」のように強酸性の中でも生き残れる菌も存在します。
常在菌が存在できないところ
健康な人の脳、心臓、腎臓、血液、子宮などの臓器には微生物は入り込めないようになっていて、もちろん常在菌も存在しません。
わたしたちの体では、微生物と共存するところと、そうではないところが別れているのです。
常在菌はどんな役割をするのか?
常在菌の果たす役割は多種多様です。
① 消化を助ける
わたしたちが食べたもののうち、特に消化しにくいもの(食物繊維など)を分解し、エネルギー源になる短鎖脂肪酸に変えてくれます。
② ビタミンの生成
わたしたちが生きていくのに必要なビタミン(ビタミンB1、ビタミンK2など)を合成し、わたしたちに与えてくれます。
③ 病原菌への抵抗
外から侵入してくる病原菌から体を守る「バリア」の役割も果たします。病原菌が体に定着するのを邪魔したり、病原菌に必要な栄養を奪い合ったり、病原菌を殺す物質を作ったりします。腸の中では、さまざまな微生物が常に「縄張り争い」を繰り広げています。
*わたしたちの抵抗力が弱ると、ふだんは害を及ぼさない微生物が感染症を引き起こすことがあります(日和見感染)。
④ 免疫
わたしたちの体において、免疫細胞の多くは腸に集中しているといわれています。常在菌は、この腸の免疫システムを「教育」する役割を担っています。体にとって無害なもの(食べ物や常在菌自身)には過剰に反応せず、有害なもの(病原菌)には適切に反応するように、免疫細胞を教育してくれるのです。
これは、アレルギーや自己免疫疾患の予防にもつながる、とても大切な働きです。ここでは、病原菌が入ってこないように、特別な「関所」のようなバリアや、体中をパトロールする「免疫細胞」が常に目を光らせています。
常在菌はどこから来るのか?
常在菌はいつ、わたしたちの体にやってくるのでしょうか。
母親の子宮内は無菌状態で、胎児も無菌です。
そのため、人と微生物との関係は、生まれた瞬間がスタートラインになります。
子どもはまず、産道を通って、母親の常在菌(ビフィズス菌や乳酸菌など)をもらいます。続いて空気や食べ物(乳)、周囲の人との接触などを通じて多くの微生物と接していきます。
これらの微生物と人体が、お互いに「戦ったり譲ったり」しながら、定着した一部の微生物が常在菌になるのです。
常在菌の数や構成する種類は成長につれて安定していき、人と微生物がともに生きる一つの生物集合体ができあがります。それがわたしたちです。
常在菌のバランスは日々変化する
わたしたちの体の中にいる常在菌のバランスは、とてもデリケートで、日々の生活習慣や環境によって大きく変化します。例えば、下記のことが影響します。
① 食事
食べたものが常在菌の「エサ」になります。食物繊維や、ヨーグルトなどの発酵食品は、腸内フローラのバランスを整えるのに役立ちます。
② 加齢
年齢とともに腸内フローラのバランスは変化します。
③ ストレス
心のストレスは、腸の動きを悪くし、腸内フローラのバランスを崩す原因になります。
④ 薬
抗生物質の過度な摂取は、病原菌だけでなく、体に有益な菌まで殺してしまうことがあります。
⑤ 運動習慣
適度な運動は、腸の動きを良くし、腸内環境を整えるのに役立ちます。
常在菌のバランスが乱れると、便秘や下痢といった消化器系の不調だけでなく、全身の健康にさまざまな影響を及ぼすことが分かってきました。腸とお腹は密接に連携しており、「腸脳相関」とも呼ばれたりします。腸内フローラのバランスが乱れると、うつ病や認知症などの心の病気や神経の病気にも関連する可能性が指摘されています。
また、アトピー性皮膚炎のようなアレルギー、肥満、動脈硬化、さらには一部のがんとも、腸内フローラの乱れが関係していることが報告されています。
常在菌はどうやって調べるのか?
昔は、常在菌、特に腸内細菌を調べるには、採取した便を培養する方法が主流でした。しかし、腸内細菌には、培養するのが難しい菌が多く含まれます。そのため、かつては腸内細菌の種類はそれほど多くないと考えられていました。
最近では、「分子生物学的手法(遺伝子の情報を使う方法)」が進歩し、培養に頼らなくても腸内細菌を詳しく調べられるようになりました。この技術によって、今では腸内細菌の種類が数百種以上あることが分かってきています。
これらの最先端の技術を使うことで、わたしたちはこれまで見えなかった常在菌の全体像を少しずつ解き明かし、それぞれの菌がどんな働きをしているのか、そして私たちの健康や病気にどう影響しているのか、より深く理解できるようになってきています。
あなたの健康は「微生物」が握っている
わたしたちの体は、単なる人間の細胞の集まりではなく、膨大な数の常在菌と共生する「超個体」とも呼ばれます。これらの微生物は、食べ物の消化、ビタミン生産、病原菌からの防御、免疫システムの教育、さらには心の状態や全身の代謝にまで影響を及ぼす、かけがえのないパートナーなんです。
あなたの腸内フローラは、生まれた瞬間から始まり、毎日の食事、ストレス、薬、年齢といったさまざまな要因によって常に変化しています。このデリケートなバランスを理解し、意識的に整えることが、現代社会で心身の健康を維持し、多くの病気を防ぐための大切なカギとなることでしょう。