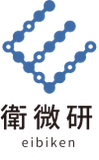概要
各種工業製品の生産後、流通や保管などの間にカビが発生するかどうかを調べる試験です。
カビ抵抗性試験と同様、カビの発生リスク(カビの生えにくさ)を調べる試験ですが、試験時にカビを接種するか否かが大きな違いです。
・カビ抵抗性試験|検体にカビを接種して培養し、カビの発生度合いを観察する。
・カビ発生有無確認試験|検体にカビを接種せずに培養し、カビの発生度合いを観察する。
試験方法
① 検体にカビを接種せずに、カビの発生しやすい環境下に置く。
(概ね20~25℃、相対湿度90%以上)
② 一定期間培養する。
③ カビなどの微生物が発生しているかを、肉眼や顕微鏡で調べ、レイティングで評価する。
カビ抵抗性試験との使い分け方は?
カビ発生有無確認試験では、あるロットから標本的に取り出した検体をカビの発生しやすい環境に置いた場合、カビが生えるかどうかを調べることができます。
一方、カビ抵抗性試験では、あるロットに限らず同様の検体がカビに汚染され、カビの発生しやすい環境に置かれた場合のカビ抵抗性(カビの生えにくさ)を調べる場合に用います。ある素材一般にカビが生えにくいといったことを示すことができます。
◆カビ抵抗性試験では、なぜカビを接種するのか?
カビを接種せずに培養し、カビが生えなかった場合、下記の2つの可能性が考えられます。
・検体にもともとカビが付着していなかった(カビに汚染されていなかった)。
・検体にカビが付着していた(カビに汚染されていた)が、検体そのものにカビ抵抗性があった(カビが生えにくい素材であった)。
カビを接種しなかった場合、上記2つの切り分けができなくなります。
そのため、カビ抵抗性試験では一定量のカビを意図的に接種し、試験を行います。
◆試験方法の選択に迷ったら
どちらの方法を選択すればよいか判断がつかないなどございましたら、試験を検討されている背景をご教示いただければ、適切な試験方法をご提案いたします。
試験実施例
・過去の製造ロットでカビが生えたことがあり、今回のロットで生えないかを確かめること。(絶対評価ができないため、過去ののロットと今回のロットで同時に試験を行うのがおすすめです)。
・あるロットにおいて製造された、抗カビ加工品と抗カビ無加工品の品質の差を比較する。(差が出ない可能性もありますし、あくまで、ある試験条件下での結果であることにはご注意ください)。
ご報告内容について
主に、試験方法と試験結果(発育度のレイティング※、実体顕微鏡画像)をご報告書に記載いたします。
画像の注意点はこちらをご覧ください。
※試験結果の表示方法
試験結果は通常、カビ発育状態をレイティングで表示します。
抗カビ性あり・なしといった判定が出るわけではありません。
レイティングの一例
| 菌糸の発育 | 結果の表示 |
| 肉眼および顕微鏡下でカビの発育は認められない | 0 |
| 肉眼ではカビの発育が認められないが、顕微鏡下で確認する | 1 |
| 菌糸発育が肉眼で認められるが、試料全面積の25%未満 | 2 |
| 菌糸発育が肉眼で認められるが、試料全面積の25%以上50%未満 | 3 |
| 菌糸発育が肉眼で認められ、試料全面積の50%以上 | 4 |
| 菌糸発育は激しく、試料全面を覆っている | 5 |
試験実施にあたって必要な情報、注意点
下記のような情報を頂ければスムーズです。
・検体数(種類数、n数※1)
・検体の性状(材質、寸法など)
・必要な書類(和文報告書以外にあれば※2)
※1 カビを接種せずに試験するため、検体のカビ汚染度合いにばらつきがある可能性があります。n数を多めに(n=5、n=10など)設定するのがおすすめです。
※2 試験方法、試験結果(発育度のレイティング※、実体顕微鏡画像)が和文の報告書に記載されます。画像データが欲しい、英文の報告書が欲しいなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。
試験期間
1~4週間
*試験の目的や条件により異なります。
費用
要お問い合わせ
*検体の種類や、試験条件により異なりますので、お問い合わせください。
不明点ございましたら、お気軽にご連絡下さい。
詳しく知りたい方はこちら:よくあるご質問 > カビ発生有無確認試験