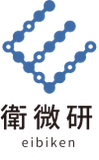保存効力試験(チャレンジテスト)とは?
保存効力試験(チャレンジテスト)は、化粧品、医薬品をはじめ、様々な製品や成分などの防腐効果を確認する試験です。
検体に試験菌液(微生物の懸濁液)を添加し、ご指定の測定日(例:2週目と4週目)に生菌数を測定します。
試験の規格や方法はどうやって選ぶのか?
保存効力試験が規定されている規格には、たとえば、下記のようなものがあります。
- 日本薬局方(JP)
- ISO 11930
- 米国薬局方(USP)
- 欧州薬局方(EP)
- 中国薬局方(PPRC)
これらの規格でも試験可能ですし、その他の試験方法でも実施可能ですが、最もよくご依頼いただく試験方法は、JPです。迷った場合は、JPを選択しておけば十分な場合がほとんどです。
JPの試験方法は、USP・EPの方法と調和合意の取れたもの(試験方法について、国際的に調和協力がなされたもの)ではありませんが、試験の流れは同様です。
また、ISOの試験方法は、国際的に認知されている方法です。
試験方法の選び方は、試験結果の用途や、試験結果の提出先の要望によりますので、どの方法がよいかは一概には言えません。
試験結果の最終提出先がある場合、ご提出先にご確認されることを推奨いたします。
また、各薬局方やISOには、化粧品や医薬品以外への適用が明記されておりません。しかし、化粧品や医薬品以外の製品や成分にたいして試験を実施することも、よく行われております。
薬局方とISOでは、「同様の性能と考えられるが、異なる試薬を用いている」など、細かい違いはありますが、試験結果に大きく影響を及ぼすと考えられるような違いはないと考えられます。
利用可能な菌株
各試験方法に規定されている菌株、もしくはご指定の菌株を使用します。
たとえば、第十八改正日本薬局方 保存効力試験法では下記5菌種であり、これらが最もご依頼の多いケースです。
- 大腸菌(Escherichia coli) NBRC 3972
- 黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus) NBRC 13276
- 緑膿菌(Pseudomonas aeruginosa) NBRC 13275
- カンジダ菌(Candida albicans) NBRC 1594
- クロコウジカビ(Aspergillus brasiliensis) NBRC 9455
「過去にトラブルがあって、製品から分離・同定された菌種がある」「検体の性質により、混入して増殖するおそれのある菌種がある」など、具体的な意図がある場合は、その他の菌種を追加することもございます。
例えば、シロップ剤などの高い糖濃度の検体には、Zygosaccharomyces rouxii(好稠性酵母)を用いることがございます。
その他、下記の菌種などをご依頼いただくこともあります。
クロカビ(Cladosporium sphaerospermumなど)
枯草菌(Bacillus subtilis(芽胞状態、栄養体))
アオカビ(Penicillium citrinumなど)
測定日の設定について
検体に試験菌液を添加して、何日後に生菌数を測定するかを決める必要があります。
最もよくご依頼いただく測定日の設定は、「2週間後(14日後)・4週間後(28日後)」です。
「1週間後(7日後)・2週間後(14日後)・4週間後(28日後)」について測定日を設定すれば、日本薬局方のすべてのカテゴリー(IA・IB・IC・ID・II)について判定が可能です。
カテゴリーの詳細は、こちらをご確認ください。
測定日は、1日後、3日後、7日後など、さらに短いスパンで設定することも可能です。
お見積りご依頼の際や、試験お申し込みの際に、具体的な測定日をご指定ください。
0日目の測定結果(試験菌液を添加した直後の生菌数)は、試験菌液の生菌数測定結果と試験菌液の接種割合を用いて理論値を算出します。
【例】10 mLの検体に対し、3.7×107 CFU/mL の試験菌液を0.1 mL接種したとき、初発菌数は3.7×107×0.1/10=3.7×105 CFU/mL
実際に0日目の生菌数測定をご希望の場合は、その旨お申し付けください。
必要な検体量
【シート状以外の検体】
可能でしたら、1検体あたり240 mL(g)以上、最低でも120 mL(g)以上ご用意ください。
【シート状の検体※】
可能でしたら、1検体あたり30枚以上、最低でも20枚以上ご用意ください。
上記が難しい場合、ご用意可能な量をご教示のうえ、ご相談ください。
※シート状の検体とは?
たとえば、パッチ状の検体や、液剤を不織布等に含浸させたような検体などを指します。
試験方法の大きな流れは変わりませんが、生菌数の測定方法が若干変わります。具体的には、適当な液で検体を洗い出し、洗い出し液の生菌数を測定する流れとなります。
この場合、液体の検体に比べ、試験菌の回収率が比較的低い傾向にあります。
必須ではありませんが、0日目(試験菌液を添加した直後)の生菌数測定を推奨いたします。
また、検体の種類に限らず、生菌数測定法の適合性確認の必要性は、どのレベルで試験データの精度を求めるかによります。
ご不明点がございましたらご相談ください。
下記リンクもご参照ください。
生菌数測定法の適合性確認とは?
生菌数測定法の適合性確認の必要性について
納期
試験申し込みを受け付けた直後から、試験菌の準備を開始し、
検体到着日からおおよそ7日以内に検体に菌を接種します。
各測定日に生菌数測定を行い、その培養結果が判明する日が速報日となります。
【例】
検体に菌を接種した日=検体到着日からおおよそ7日以内
7日目速報:検体に菌を接種した日から14日後
14日目速報:検体に菌を接種した日から21日後
28日目速報:検体に菌を接種した日から35日後
ご報告書発行:検体に菌を接種した日から42日後
*検体の種類や検体数によりますので、具体的な日にちは
検体到着日、検体の種類、検体数をご教示の上、お問い合わせください。
試験結果の記載方法
標準的な形式では生菌数(初発菌数および各測定日の生菌数)のみ記載します。
試験結果の判定をご希望の場合、ご希望のカテゴリーをご教示ください。
カテゴリーの詳細・試験結果の判定基準については、下記のページをご確認ください。
保存効力試験(チャレンジテスト)の判定基準
化粧品や医薬品以外の検体を用いた試験
化粧品や医薬品以外の検体での測定も受託しております。
下記に挙げた検体以外にも試験実施が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
粉体を用いて保存効力試験をすることはできますか?
固形石鹸を用いて保存効力試験をすることはできますか?
シートを用いて保存効力試験をすることはできますか?
※保存効力試験に関するよくあるご質問はこちら
不明点ございましたら、お気軽にご連絡下さい。
詳しく知りたい方はこちら:よくあるご質問 > 保存効力試験