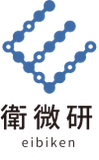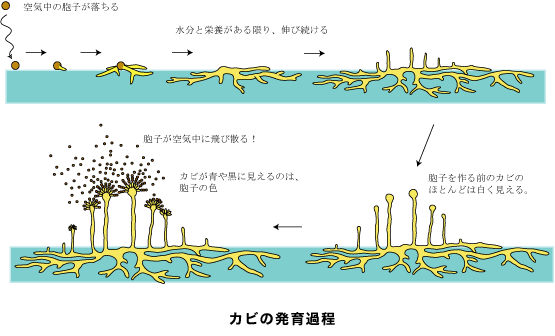カビとは?
カビは、「真菌」とよばれる菌類の一群です。酵母やキノコも真菌のなかまです。
カビは、「菌糸*」がたくさん集まって、網の目のように広がり、菌糸体とよばれるかたまりになったとき、はじめてわたしたちの目に見えるようになります。
* 糸のような細胞。先端から栄養や水分を吸収しながら、伸びていく。
わたしたちが、パンや鏡餅、果物などの表面にカビが生えたと気づくのは、この状態のときです。肉眼で見えている時点で、カビの成長はかなり進んでいると考えていいでしょう。
成熟した菌糸は、胞子を作ります。この胞子にはカビの種類によってさまざまな形や色があり、胞子の色がそのままカビの色であることもあります。たとえば、クロコウジカビの胞子は黒色、アオカビの胞子は青色をしています。
一方、菌糸の色は透明だったり、白色だったりすることが多いです。ふだん、わたしたちが見ている黒や青などのカビの色は、多くの場合、胞子の色なのです。
カビは、現在までに約10万種知られています。カビは、わたしたちに有益な働きをしたり、害を及ぼしたりしています。
ちなみに、カビは特定の生物分類を指すわけではありません。糸のような形態をもち、「ふわふわ」「粉っぽい」「ぬめぬめ」といった外見をもつ真菌の一般的な呼び名です。
カビの発育過程
カビは次のように発育します。胞子が、植物の種子みたいなものだと思っていただければ、分かりやすいかもしれません。
① 胞子が落ちる
空気中を漂っていた胞子が、物の表面(基質)に落ちる。
*顕微鏡がないと観察できない。
② 菌糸が伸びる
水分・栄養・温度・酸素の条件がすべてそろったときに、空気中または基質中に菌糸を伸ばす。
③ 胞子の形成・拡散
成熟した菌糸が胞子を形成する細胞を作り、胞子を空気中に拡散する。
*青・黒・緑などの色は主に胞子の色。
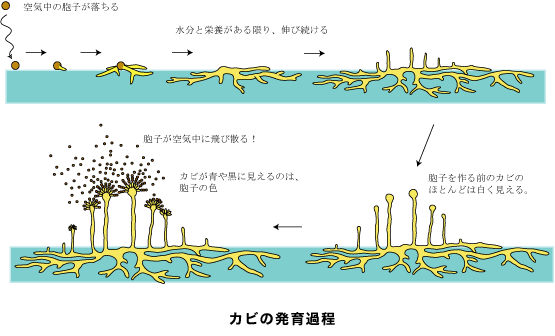
「カビの個数」ってなに?
実験などでいう「カビの個数」は、寒天培地で培養したコロニー(カビのかたまり)の数です。胞子1個から1個のコロニーができるため、「胞子の数=カビの個数」として数えられています。
ただ、実際には胞子・菌糸・菌糸体など、カビには成長段階があります。植物に種子や茎、葉、花などの状態があるのと似ています。そのため、個数だけで、カビの発育の程度は判断できません。
カビの役割
カビは、生態系や人間にとって、さまざまな役割を果たしています。
「カビ=悪者」と考えがちですが、有益な面、不利益な面の両方を持ち合わせています。
有益な働き
① 自然界の「分解者」
枯れた植物や死んだ動物などの有機物を分解し、栄養素を自然界に循環させる。
② 食品の生産
しょうゆ、味噌、酒、かつお節、チーズなど、さまざまな食品に使われる。
③ 医薬品の製造
ペニシリン(アオカビ(Penicillium)が合成する抗生物質)などが有名。
有害な影響
① 物の腐敗・劣化
食品や建築材料などで発育し、腐敗・劣化をもたらす。
② 感染症の原因
抵抗力の落ちた人に対して、カビの種類や暴露量によっては、感染することがある。
家にはどんなカビがいるの?
アオカビ(Penicillium)、コウジカビ(Aspergillus)、クロカビ(Cladosporium)は、一般家庭で見られる代表的なカビです。
しかし、同じ家でも生えるカビの種類が変わってきます。
お風呂、キッチンなどの水周りには黒色酵母様菌(Aureobasidium)、フォーマ(Phoma)、ススカビ(Alternaria)、クロカビ(Cladosporium)などが、その他の箇所にはカワキコウジカビ(Eurotium)、コウジカビ(Aspergillus)、アズキイロカビ(Wallemia)などの発育が見られます。
お風呂でよく見かけるピンク色のぬめりは、実はカビではなく、酵母や細菌でできています。多くの方がお風呂で黒や褐色の変色を経験し、それらをカビと認識しているため、「お風呂=カビ」という印象が強いかと思います。そのため、ピンク色に見える部分も、実際にはカビではないにもかかわらず、「ピンクカビ」と呼ばれるようになったと考えられます。
家の中で言うと、アルミサッシにカビが生えることもあります。これはカビがアルミを好んで生えているわけではありません。カビがどこに付着したい、どこで発育したいといった意思はありません。そこに汚れが付着し、熱伝導率の高いアルミサッシが、外気との温度差によって結露し、カビの発育に不可欠な水分を供給してしまうためです。
カビが生えるとどうなるの?
住環境でのカビの影響は、美観を損ねるだけにとどまりません。
① アレルギー疾患
アトピー性皮膚炎や喘息などの原因になる可能性がある。
② 感染症
免疫機能が低下した人に対して、まれに感染を引き起こすことがある。
③ カビ毒
一部のカビはカビ毒を産生し、健康に悪影響を及ぼす可能性がある。
④ ダニのエサ
カビはダニのエサにもなり、衛生面で注意が必要。
「カビ取り剤」や「防カビ剤」製品の安全使用ガイドなどについては、日本家庭用洗浄剤工業会(家洗工)のホームページをご覧ください。
カビの発育に適した条件とそれに応じた対処法
カビの発育には、条件がすべてそろうことが必要です。
発育条件がそろうまでは、カビは休眠状態でいることが可能です。多くの場合、一般環境下では、カビの発育に適した条件と適していない条件を繰り返すため、カビはゆっくりと発育し、わたしたちの目に触れるときには、かなり成長した状態で現れます。
① 水分
多くのカビの発育には、80%以上の湿度を必要とします。
カビによっては、60~70%程度でも発育が可能なものも存在します。
しかし、この湿度の話はあくまで発育が可能な環境についてのことで、注意すべき点があります。
たとえば、表面が濡れている箇所は、周囲の湿度が低くてもほぼ100%に近い湿度になります。また、押入れのようなある程度の密閉空間に水分を含んだ物を入れると、その空間自体の湿度が周囲の湿度に関係なく高まります。実際に室内でカビが発育している場合、これらの部分的な水分の存在や密閉空間内の高湿度の影響が非常に大きいと考えられます。
② 栄養
木材、紙、ほこり、食べ物など、さまざまな有機物を栄養に発育することができます。
③ 温度
ほとんどのカビは20~30℃を発育に最適な温度帯としています。
これ以上またはこれ以下の温度帯でも、ゆっくりと発育することが可能です。
④ 酸素
一部の細菌と異なり、カビの発育には必ず酸素が必要です。
対策のポイント|水分コントロールがカギ!
酸素は人間にとっても必要です。温度は、人間にとって快適な温度と被ります。よって、酸素や温度を制御するのは非現実的です。栄養は、定期的な清掃などによってある程度は除去できますが、限界があります。
カギとなるのは水分です。
結露を除去する、漏水を修理する、換気を改善する、除湿機を使用するなどのことは、有効な予防策です。
これらの予防策を行っても、カビが生えてくる場合は、防カビ剤の使用も検討しましょう。
カビは基質の表面だけでなく、内部にも菌糸を伸ばす可能性があるので、単に表面を清掃しても、完全に除去できていない場合があります。
お風呂のタイルの目地に発生するカビは、その最たる例です。