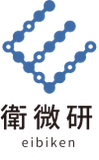-
検体・各種試験
抗菌加工試験片と無加工試験片を両方準備しなければなりませんか?
結論 原則的には、両方準備して結果を比較する必要があります。無加工試験片が準備できない場合は、規定の代用品を使用することもできますが、試験結果の解釈には注意が必要です。 前提:原則は両方準備して比較 何らかの基材に抗菌加 […] -
検体・各種試験
AATCC TM100はどのような試験手順ですか?
AATCC TM100 Test Method for Antibacterial Finishes on Textile Matelialsの試験手順は下記のとおりです。 【試験方法】検体(試験片)を直径4.8±0.1 […] -
検体・各種試験
JIS L 1902(ハロー法)はどのような試験手順ですか?
JIS L 1902 繊維製品の抗菌性試験方法及び抗菌効果(ハロー法)の試験手順は下記のとおりです。 【試験方法】試験菌液(ブイヨン培地を用いて調製)1 mLを滅菌シャーレに入れ、普通寒天培地と混釈したものを試験培地とす […] -
検体・各種試験
JIS L 1902(菌液吸収法)はどのような試験手順ですか?
「JIS L 1902 繊維製品の抗菌性試験方法及び抗菌効果(菌液吸収法)」の試験手順は下記のとおりです。 【試験方法】0.4 gの検体に試験菌液(1/20ニュートリエント培地を用いて調製)を0.2 mL接種し、37℃で […] -
検体・各種試験
【JIS Z 2801・JIS L 1902】無加工試験片で菌が増殖しない(試験不成立)こともあるのですか?
結論 無加工試験片であっても実は多少の抗菌性がある場合があり、試験が不成立になることがあります。その場合、試験条件を規定から変更して試験をすることも可能です。適切な試験条件を見つけるための予備試験が別途必要です。 前提 […] -
検体・各種試験
JIS Z 2801はどのような試験手順ですか?
「JIS Z 2801 抗菌加工製品−抗菌性試験方法・抗菌効果」の試験手順は下記のとおりです。 【試験方法】検体(試験片)に試験菌液(1/500ニュートリエント培地を用いて調製)を接種し、ポリエチレンフィルムを被せて35 […] -
検体・各種試験
どのような試験法がありますか?
抗菌性試験・抗カビ性試験と一口に言っても方法が一通りとは限りません。検体の性質や性状、試験目的等により、試験方法を検討していく形となります。なお、唯一正解の試験方法があるわけではありませんし、得られた結果はある一定条件下 […] -
検体・各種試験
生菌数測定の必要検体量を教えてください。
日本薬局方 微生物限度試験法 生菌数測定試験に必要な検体量は下記の通りです。なお、この試験法は三薬局方での調和合意に基づき規定された試験法ですので、米国薬局方(USP)、欧州薬局方(EP)で試験を行う場合も同様です。 ・ […] -
検体・各種試験
培地性能試験とは何ですか?実施する必要はあるのですか?【微生物限度試験】
培地性能試験とは? 試験に用いる培地に、菌を適切に検出する性能があるかを確認する試験です。 培地性能試験の方法は?弊社で選択可能な培地性能試験のパターン(a・b)とは? 試験に用いる培地と、比較用の培地にそれぞれ菌を接種 […] -
検体・各種試験
【微生物限度試験・保存効力試験(チャレンジテスト)】適合性確認試験とは何ですか?適合性確認試験を実施する必要はあるのですか?
保存効力試験(チャレンジテスト)の項目に同様のFAQを掲載しておりますので、ご参照ください。 -
検体・各種試験
試験実施にあたり、必要な情報を教えてください。
試験目的によって、試験実施項目を選んでいただく必要がございます。 生菌数測定試験総好気性微生物数、総真菌数(試験方法について、特にご希望がないようでしたらカンテン平板塗抹法を用いますが、ご希望に応じてカンテン平板混釈法も […] -
検体・各種試験
どのような規格を取り扱っていますか?
日本薬局方(JP)、米国薬局方(USP)、欧州薬局方(EP)、中国薬局方(PPRC)、ISO17516、ISO18416、ISO221150、ISO22717、ISO22718、ISO11290、ISO21149、ISO […] -
検体・各種試験
どのような試験ですか?
検体に含まれている汚染微生物の菌数を調べる「生菌数測定試験」と検体に特定の微生物が存在するかを調べる「特定微生物試験」で構成されています。試験目的に応じて、試験項目を選択いただく形となります。 -
検体・各種試験
欧州薬局方(European Pharmacopoeia, EP)保存効力試験の判定基準を教えてください。
【非経口製剤、点眼剤、子宮内および乳腺内に適用する製剤】 <A criteria>*推奨の達成基準・細菌→6時間後:接種菌数に比べ2log以上の減少 24時間後:接種菌数に比べ3log以上の減少 […] -
検体・各種試験
【保存効力試験】試験結果はどのように記載されますか?
標準的な形式では生菌数(初発菌数および各測定日の生菌数)のみ記載します。試験結果の判定をご希望の場合、ご希望のカテゴリーをご教示ください。