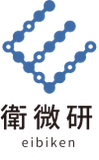検体・各種試験
-
検体・各種試験
台湾FDAの化粧品PIF制度に関連する試験はできますか?
台湾FDAの化粧品PIF(Product Information File)制度に関連する試験も実施可能です。 ◆微生物限度試験化粧品中微生物之檢驗方法(Methods of Test for Microorganism […] -
検体・各種試験
EN 13697に基づいた硬質表面キャリア法の試験はできますか?
実施可能でございます。 試験概要 ①試験片の準備直径2cmのステンレス鋼製ディスクを準備する。②試験菌液の調製負荷物質(汚れ成分)として、0.03%または0.3%のウシ血清アルブミンを添加した試験菌液(約107~108 […] -
検体・各種試験
フケの防止に関する試験はできますか?
フケを防止するかどうかを直接調べることは困難です。 フケの防止を製品に明記することはできませんが、例えば、Malassezia属の菌で試験をして、この菌種がフケの原因菌の一種とされている、などと記載することで、嘘のない範 […] -
検体・各種試験
抗菌試験、除菌試験、MIC試験の検体濃度はどうやって決めればいいですか?
検体の想定使用濃度、効果を期待する濃度をもとに決めていただく必要がございます。 複数濃度設定いただいても構いません。 想定使用濃度について、ワーストケース(検体濃度が薄い)などを想定して決めていただいてもよろしいかもしれ […] -
検体・各種試験
抗菌性、除菌性を謳いたい場合、どのような試験が適切ですか?
抗菌や除菌、抗カビ、防カビといった言葉には、具体的な定義がございません。 また、「どのような試験を行えばどのような効果が謳える」といった決まりもございません。 試験の結果から、具体的にどのようなことを言いたいかによって、 […] -
検体・各種試験
栄養濃度は試験結果に影響しますか?
試験をしたときに、添加した栄養濃度は、試験結果に大きく影響を及ぼす要素です。 一般的に、栄養濃度が高ければ菌に有利に働きます。 また、有機物が検体と反応し、検体の効果が弱まる可能性もございます。 JIS規格などをもとに、 […] -
検体・各種試験
「防カビ性何年相当」などといったことを調べることはできますか?
残念ながら、「何年相当の防カビ性」といったことを調べる術がございません。 「~年相当」といったような記載が、Web上などで散見されますが、JISなど文書化された試験方法に、そのような解釈は記載されておりません。 また、一 […] -
検体・各種試験
カビ抵抗性試験の合格基準を教えてください
JIS Z 2911など、カビ抵抗性試験の各種文書には、合格基準のような記載はございません。 しかし、既存品と変更品がある場合、同一条件で試験をすれば、比較はもちろん可能です。 -
検体・各種試験
バスタオルはどれくらいで洗ったほうがいいですか?
前提として、「菌数がこれくらいであれば洗ったほうがよい、洗わなければならない」といった目安はございません。 バスタオルの菌数は、バスタオルの使用条件・保管条件によっても大きく変わります。 使用条件等をご指定いただければ、 […] -
検体・各種試験
規格通りに試験してほしいのですが
JISなどの試験方法は、単に、よく行う試験を文書化したものです。 試験背景や検体などによって、目的に合わないことが多くあります。 菌に対する効果などを調べる際、JISなどの試験文書に沿って試験を行う必要性があるわけではあ […] -
検体・各種試験
抗菌性、除菌性が十分かどうかを確かめたいのですが?
抗菌性、除菌性には定義、基準があるわけではありませんが、一般的には、1/100または1/1000以下に菌が減少していることをもって、抗菌性、除菌性があるとすることが多いです。 しかし、どれほどをもって「十分」とするかにつ […] -
検体・各種試験
検体によって試験方法は決まりますか?
残念ながら、決まりません。試験の背景、目的によって、試験方法を協議する必要がございます。 「~製品を対象とする」といった記述のある試験文書がございますが、「~製品であればそのような記述のある試験文書で必ず試験しなければな […] -
検体・各種試験
トイレ砂の抗菌試験はできますか?
可能でございます。 「抗菌」という言葉は明確な定義を持ちませんので、具体的にどのような効果を調べたいかをお伺いし、弊社から試験方法をご提案して、承認いただく流れが一般的です。 定義は不明確ではありますが、「抗菌」といえば […] -
検体・各種試験
JIS Z 2911のプラスチックの試験では方法A・Bどちらが適切ですか?
試験の目的により変わってきます。 方法Aは、栄養を添加せずに行う試験ですので、検体自体がカビの栄養になるかどうかを調べる目的で用いられます。 方法Bは、栄養を添加して行う試験です。 表面汚染を想定するときなどに用いられま […] -
検体・各種試験
医薬品や医薬部外品に対してGLP基準の試験はできますか?
医薬品や医薬部外品などに対しても、GLP基準に従って、除菌・殺菌等に関する試験を行うことが可能です。しかし、GLP基準といっても、要求される書類・書式はその要求元によってさまざまです。したがって、内容の協議があらかじめ必 […]