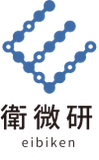JIS等の文書で、抗菌活性値や抗かび活性値という表現があります。
これは、「対照と比較して、菌数・菌量がどれくらい減少しているか」を、対数を使って分かりやすく表しているものです。
【例】
JIS Z 2801の抗菌試験を行った。このとき、培養後の生菌数は次の通りであった。
・無加工試験片:3.6×107 CFU/cm2
・抗菌加工試験片:1.4×103 CFU/cm2
このときの抗菌活性値は、
log10(3.6×107)-log10(1.4×103)≒7.56-3.15≒4.4
と求まる。
つまり、104.4 倍 (約2万5千倍)の差(減少度合い)といえる。
試験結果をどう判断してよいか迷われるようでしたら、お気軽にご相談ください。
また、下記の関連FAQもご参照ください。
・抗菌活性値、抗カビ活性値はどれくらいあればいいのですか?
・JIS Z 2801における抗菌活性値の算出方法と判定基準を教えてください
・JIS L 1902(菌液吸収法)における抗菌活性値の算出方法と判定基準を教えてください
・報告書の結果を見たのですが、これは抗菌効果があると言っていいのですか?判定基準はありますか?
・【JIS Z 2801】菌が検出されない場合の生菌数の常用対数値が-0.2となっていますが、なぜですか?
・栄養濃度は試験結果に影響しますか?