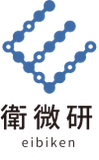-
よくあるご質問
同じ材質・素材の製品であれば同じ結果が得られますか?
同じ材質・素材の検体で同様の試験をすれば、同様の結果が得られる可能性があると推測はできますが、その解釈を許容するかどうかは、各種規格において明確な規定がされておらず、貴社内もしくはデータの提出先で適宜ご判断いただく形とな […] -
よくあるご質問
試験片のサイズを大きくすれば抗菌性が上がりませんか?
抗菌効果は、菌と抗菌物質が接触して発揮されるものと考えられます。試験片のサイズを大きくすると抗菌物質の量は増加すると考えられますが、単位面積あたりの抗菌物質の量は変わらず、菌と抗菌物質の量的関係が変化しないと考えられるた […] -
よくあるご質問
抗菌効果の持続性を調べる方法はありませんか?
例えば、噴霧や塗布をして用いる液体の検体であれば、下記のような方法が考えられます。 貴社または弊社にて試験片(※1)に検体を接種(※2)し、保管状況を想定した環境(※3)にご指定の期間(※4)保管する(※5)。その後弊社 […] -
よくあるご質問
【抗菌性試験・抗カビ性試験/除菌試験】試験後の試験片の画像が欲しいのですが?
試験片自体を肉眼で見ても、試験菌や菌数の差が見えるわけではありませんので、基本的に試験片の画像は提供しておりません。それぞれの生菌数測定結果のイメージを表したシャーレ画像でしたら、撮影してご提供が可能ですが、別途料金がか […] -
よくあるご質問
【抗菌性試験・抗カビ性試験】報告書に画像は付きますか?
抗菌性試験・抗カビ性試験や除菌試験のご報告書には、標準的に画像が貼付されません。ご希望がございましたら、試験結果(生菌数)をイメージした画像として、試験とは別に試験菌をシャーレで培養した画像をご提供することは可能です※。 […] -
よくあるご質問
JIS L 1902の試験を繊維以外の検体で行いたいのですが?
繊維以外の検体でも、吸水性のある素材であれば原則試験実施が可能でございます。 -
よくあるご質問
試験n数を教えてください。
通常n3で行うことが多いです。検体が十分に準備できない、スクリーニングのために大量に実施したいなど、目的によって、n1など、n数を適宜変更することも可能です。 -
よくあるご質問
試験前に検体の滅菌処理は行いますか?
ご指示がない限り、検体の滅菌処理は通常実施いたしません。もしご希望でしたら、高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)、乾熱滅菌、エタノール殺菌など、方法を含めてご教示いただけますと幸いです。 -
よくあるご質問
JIS R 1705はどのような試験手順ですか?
「JIS R 1705 ファインセラミックス-光照射下での光触媒抗かび加工製品の抗かび性試験方法」の試験手順は下記のとおりです。 【試験方法】検体(試験片※)に試験胞子液を接種し、フィルムを被せた後、25±5℃で24時間 […] -
よくあるご質問
JIS Z 2801の試験において50×50mmの試験片以外でも試験はできますか?
試験実施可能です。事前に寸法・形状についてご連絡いただければ幸いです。 【小さな試験片の場合】通常サイズの試験片より小さいため、通常よりも試験結果にばらつきが出やすい傾向となりますので、あらかじめご了承ください。 【円形 […] -
よくあるご質問
検体は試験片のサイズに裁断して送る必要がありますか?
比較的容易に裁断できる検体であれば、大きめの面積の検体をお送りいただき、弊社で裁断することも可能です(別途費用が掛かります)。ただし、貴社で裁断いただいたほうが試験準備の工程が減り、よりスムーズに本試験に取り掛かることが […] -
よくあるご質問
JIS Z 2801、JIS L 1902、JIS L 1921に規定されている抗菌試験はできますか?
JIS Z 2801(硬質面に対する抗菌効果を調べる試験)、JIS L 1902(繊維など吸水性のある検体)は多くご依頼を頂く試験であり、実施可能です。JIS L 1921(ATP量の測定により抗カビ効果を調べる試験)も […] -
よくあるご質問
どのような規格を取り扱っていますか?
JIS L 1902、JIS Z 2801、JIS L 1921、JIS K 3835、各種ISO規格、AATCC 100、AATCC 147、SEK統一試験法、抗菌製品技術協議会(SIAA) シェーク法など各種規格を取 […] -
よくあるご質問
規格に規定されていない菌種・菌株でも試験はできますか?
目的に応じて、試験規格から菌種※やその他条件を一部変更し、試験を行うことも可能ですし、しばしば行われます。 ※例えば、JIS Z 2801では黄色ブドウ球菌と大腸菌、JIS L 1902では黄色ブドウ球菌と肺炎桿菌が規定 […] -
よくあるご質問
シェーク法はどのような試験手順ですか?また、どのようなときに選択しますか?
抗菌製品技術協議会 シェーク法の試験手順は下記のとおりです。シェーク法は検体が平滑でない特殊な形状または小物の場合に適した抗菌試験方法です。5cm×5cm等の試験片が作製できるような検体の場合、JIS Z 2801等を用 […]